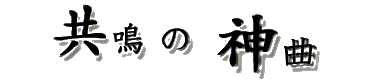Sympathizer16... この手はなぜ届かない
アニュー・リターナーが、死んだ。
刹那は言った。
後で恨めば良いと。
「お前のせいで…っ、お前のせいでアニューはっ!!」
怒りに任せた拳は、無重力上でいとも簡単に刹那を吹っ飛ばした。
ライルは後ろへ吹っ飛んだ刹那へ掴み掛かり、再度殴り掛かる。
「ロックオン!止めろ!」
アレルヤの制止は、彼にはまったく聞こえていない。
「アニューは戻ろうとしていた!!戻ろうとしていたのに、それをお前は…!!!」
何度目かに振り下ろそうとした腕が不意に掴まれ、止まる。
細く見える指が、ぎりぎりとライルの右腕に食い込んだ。
「…放せ」
「放さない」
「放せ」
「……」
左手で刹那の胸ぐらを掴み上げたまま、ライルは右腕を掴む人物へ怒鳴った。
「放せっつってんだよティエリアッ!!」
その要求通りにふ、と右腕を掴む力が緩んだその瞬間。
パァンッ!!とライルの頬に逆側から張り手が飛んだ。
目を丸くしたのは、どうすれば良いのかと状況を見守っていたアレルヤとソーマ、沙慈。
そして頬を張られたライルだった。
慣性の法則に従い、彼の身体は刹那から離れる方角へと流れる。
「…大丈夫か」
ライルを張り飛ばした左手を収め、ティエリアは刹那の殴られた頬をそっと撫でた。
切れた唇から流れる血を拭い、暗い部屋の中でも分かる赤に眉を寄せる。
「ティエリア…」
相手の名前を呼ぶ以外に、刹那に出来ることは無い。
ティエリアは刹那を後ろに庇うように立ち、体勢を立て直したライルと向かい合った。
「てめぇ…何しやがる…」
低くなった声は、沸点をとうに越えた証。
ライルは相手を射殺せそうな程に怒りを溜めた目を、ティエリアへ据えた。
「そいつはアニューを殺したんだ。戻ろうとしたアニューを!」
激昂ではない、怒りを押し殺すライルへティエリアは問い返す。
「では訊くが、なぜ君が殺される寸前だったんだ?ロックオン・ストラトスともあろう者が」
「黙れ!そいつがアニューを殺したんだ!!アニュー・リターナーをっ!!」
「そんな事実は誰だって知っている!!!」
ティエリアの怒声が、ライルの怒声を遮った。
「刹那が彼女を撃った!だから刹那は、お前の怒りを受け止めることを当然としている!」
「だったら!!」
返そうとしたライルの言葉を、ティエリアは皆まで言わせなかった。
「それで誰もが納得すると思うなっ!!!」
アレルヤは、こんなにも怒りを露にするティエリアを初めて見たと思った。
ロックオン…ニール・ディランディのときも、ここまでではなかった。
誰もが、常に冷静であるティエリアしか見たことがない。
組織を再建したティエリアは、組織それ自体を動揺させないためにそうであることを己に課していた。
4年前とは違う彼を、古参からのメンバーは誰もが知っている。
だからこそ、怒りと悲しみで腑が煮えくり返っているはずのライルでさえ呆気に取られた。
ティエリアは鋭くライルを見返す。
「お前にとって、彼女は大切な存在だった。失えないものだった。
俺はお前ではないから表面しか分からないが、もっと大きなものだったのかもしれない」
淡々と紡がれた彼の言葉に、絞り出すようにライルは答えた。
「…そうだよ。アニューは、彼女は、俺にとって新しい世界だった。
父さんも母さんもエイミーも、兄さんも奪われた俺にとって、アニューは…!」
すっとティエリアの目が細められた。
「大事なものを傷つけられて憎悪するのは、お前だけじゃない」
その目を改めて見た瞬間、ゾッと背筋が凍りついた。
部外者であるはずのアレルヤたちでさえ、喉が乾いて張り付いている。
「俺の…いいや、"俺たち"にとっては、刹那がお前にとってのアニュー・リターナーと同じだ。
…いや、比べるのはアニュー・リターナーにも失礼だな。天秤に掛けても答えは明白なのだから。
だから俺は、刹那を傷つけるお前が許せない」
言葉は刃になるのだと、昔誰かが言っていた。
言葉は身体を傷つけず、けれど精神(こころ)を引き裂き見えぬ血を流させると。
無音となったその空間で、もういい、と刹那はゆるゆると首を横に振った。
「もう、良いんだ。ティエリア」
だからもう、止めてくれ。
ティエリアの手を取り、刹那は静かに目を伏せる。
彼の言葉は、誰に対するものだったのだろうか。
ティエリアに対して、ライルに対して、それとも自分に対して?
−−−するり、と手にしていたグラスが滑り落ちた。
カシャーン!と甲高く響いた音に、リジェネはハッと顔を上げる。
「シン…?」
王留美の屋敷内はほぼ全てが調度品で飾られており、硝子の割れる音がしたからといって、それがキッチンとは限らない。
しかもこの階は2階である上に、使用人がきっちりと持ち場を果たす屋敷だ。
…音の聞こえた方角にある客間の2つ目に、彼は居た。
砕けてしまったのは、火の入っていない暖炉の上に飾ってあったワイングラスらしい。
シンは部屋の入り口ではなく庭を臨む窓を向いて立っていて、リジェネには表情が窺えない。
「…行かないと」
小さく呟かれた声に首を傾げると同時に、ぎょっとして彼に駆け寄った。
「危ない!」
寸でのところで、リジェネはシンを抱き寄せた。
グラスが落ちたのは、毛足の長い絨毯と暖炉の間。
おそらくは、気まぐれにグラスを手に取ってみただけだったのだろう。
彼の履物は絨毯のソファの足元にある。
窓の方へ足を踏み出そうとしたシンは、砕け散った硝子を危うく踏むところだった。
足を踏み出せないように抑えるリジェネから離れようと、シンは抵抗を見せる。
「放せ!早く、行かないと」
リジェネはまったく筋の見えない言葉に、再度首を傾げた。
「行くって、どこへ?」
「刹那のところに決まってる!」
彼の双子の兄は、宇宙に居るはずだ。
(行くにしても今は、リボンズの作戦が進行中のはず)
「どうしてまた…突然?行くにしても、相当な距離がある」
「それくらい知ってる!知ってるけど…!」
このままでは本当に、硝子の上に足を踏み出しかねない。
そう感じたリジェネがその場から放そうと一歩引くと、シンは本気で抵抗し腕を振り払った。
「邪魔するな!早く行かなきゃ刹那が…!!」
こちらを振り向き叫んだ彼に、リジェネは驚いた。
「シン…君、泣いていたの?」
透明な雫が、次々と頬を伝って流れ落ちている。
けれどシンは首を振った。
「違う。これはオレじゃない」
「え?」
不可解な顔をしたリジェネに、涙を拭いながらシンは告げる。
「刹那が、泣いてるんだ」
いくら拭っても、涙が途切れる気配はない。
だから、早く行かないと。
そう言って今度は部屋を出ようとしたシンを、リジェネは腕を掴むことで止める。
「放せっ!!」
掴んだ手の力を少しでも緩めれば、彼は駆け出してしまう。
リジェネは放すまいとさらに力を込めた。
本気の怒りが込められた眼で彼に睨まれるのは、初めてだった。
「…無理だよ。物理的な距離の問題だけじゃない」
それでも静かに、事実を述べる。
赤いルビーのような眼が、さらなる怒りに歪んで揺れた。
「アンタはっ、アンタは失くしたことがないからそんなことが言えるんだっ!!!」
生き別れて、何年だったのか。
ようやくのことで再会出来たあの日以降、刹那は幾度となく訊いてきた。
『お前は本当に、"ここ"に居るんだな?』と。
(ねえ、刹那。オレは、刹那にそれを問いたいよ…)
せめて今、彼の隣にティエリアが居れば良いと心から願う。
涙は、いつまで経っても止まらなかった。
どれだけ願っても。
その哀しみを、半分でも
ー 背負うことが出来れば良いのに ー
09.2.22
カタロン組の方が後に書いたものですが。
リジェシンが成立してないと、加筆の後半部分が有り得ないのです(苦笑)
なので順番が逆という…。
前の話へ戻る←/→閉じる