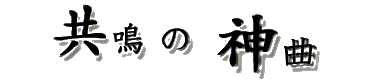Sympathizer15... 奈落の底に空を見る(後)
ほんの一瞬前まで、通話していたはずの相手。
それが、なぜここに居る?
「なん、で…?」
とてもじゃないが、信じられない。
現実に起こっていると分かっていても、現状について行けない。
硝子越しに驚愕の眼差しでこちらを見つめるシンに、リジェネは笑った。
「言ったでしょう?"座標さえ分かれば、そこへ辿り着ける"って」
『ヴェーダ』に直接リンクすることで、存在を転送することが出来る。
といっても、それはすべてのイノベイターが出来るわけではない。
「これが可能なのは、Lv.5以上のアクセス権を持っている者に限られるけれど」
全アクセス権を握るリボンズ、Lv.5までの権限を持つリジェネ。
そして、
(かつて最深層Lv.7までアクセスすることが出来た、ティエリア・アーデ)
彼は本来ならば、リボンズと対等な存在であるはずだった。
「…アンタ、実体なのか…?」
シンはおそるおそるといった体(てい)で振り向いた。
同時に投げた問いには、明確な肯定が返る。
リジェネ・レジェッタは、確かにそこに立っていた。
服装は初めて見る、白と青系に分かれたもの。
彼は持っていた通信機の電源を落とした。
「君が、王留美の屋敷に居てくれて良かった」
そうでなければ、またリボンズに目を付けられるところだった。
軽く肩を竦めたリジェネは、静かに1歩踏み出す。
「…良かったって、何が」
反射的に1歩後ずさって、シンは問い返した。
なぜ、彼から離れようとしたのか。
今まで1度だって、逃げるようなことはしていなかったのに。
(分かってる。怖いんだ、オレは)
『イノベイター』という存在が、人間とどう違うのか。
分かっていたつもりで、まったく分かっていなかったのだ。
(だって、同じだった。何が違うのか分からなかった)
同じように話して、歩いて、食べて、笑って。
(…それなのに)
このたった数分で、相手に恐怖を覚えてしまった。
人間ではない化け物であると、思ってしまっている。
それだけは決して、抱いてはいけない感情であるのに。
(だってそれは、)
それは『ラグナ』の共鳴者である刹那と、同じ『イノベイター』であるティエリアへの冒涜だ。
「違うよ」
「え?」
シンの自己嫌悪を見透かしたように、リジェネは言った。
「刹那・F・セイエイはおそらく、人類で最初の『革新者』だ。彼は人の可能性を示しているに過ぎない。
ティエリア・アーデは逆に、『イノベイター』でありながら『自分は人間だ』と言い切った。
彼らは、私たちとは違う」
もっともこれは、私の個人的な考えに過ぎないけれど。
そう言ってリジェネが浮かべた笑みは、どこか諦観していた。
(知ってる。オレは、その顔を見たことがある…)
ひょっとして、容姿以外の部分でティエリアに似ているんじゃないかと思った、あの時。
自分は先程まで、この人物と何を話していた?
驚愕しか映さない目を1度伏せて、ゆっくりと息を吐く。
「…アンタは、オレに何を求めてる?」
携帯電話をポケットへ仕舞い、シンは真っ直ぐにリジェネを見据えた。
軽く握り締められた拳は、彼が恐怖と闘ってなお立っている証だ。
しかし宝石色の眼は、空の一等星のように強く輝いている。
リジェネはその強い眼差しに、危険を冒してでもここへ来て良かったと、本気でそう思えた。
(…本当に、どうしてだろうね?)
最初は、『刹那』と『ラグナ』に近づくための手段であったはずなのに。
「…君に、話しておこうと思ったんだ」
『イノベイター』のこと、『ヴェーダ』のこと、イオリアの計画のこと、そして。
「私のことを」
シンの眼が大きく見開かれた。
「なんで…」
そんなこと、こちらが訊きたい。
けれど訊いたところで、求める答えは返って来ないだろうと思う。
「そろそろ不味いと思ったから」
だからリジェネは、そうでない別の答えを口にする。
「不味いって、何が?」
まったく的を絞らない言葉は、不可解であるばかりだ。
眉を寄せたシンに対し、リジェネはわずかに目を伏せる。
「私が君のことを隠し通せるのも、限界が近いから」
意味が分からず首を捻っている間に、彼はシンと同じように窓に近づき空を見上げた。
「脳量子波っていうのは、相手と自分の思考を直接繋ぐもの。
だから相手の考えていることが直接伝わるし、その人が何かを思い出していれば記憶だって読める」
いわゆる、精神感応力(テレパシー)のようなものだろうか。
刹那やティエリアは『ラグナ』の声が聞こえると言うけれど、シンには声らしきものは聞こえない。
「つまり、うっかりするとすべて筒抜けになってしまう。
そうならないように、私たちは自分の思考の一部に鍵を掛ける」
抽象的で分かりづらいが、器用だなと思った。
「特に大事なものは、厳重にね」
鍵の掛かった宝箱を別の宝箱に入れ、さらに鍵を掛ける。
それを幾度となく繰り返し、誰にも見られないように。
「私は他の大事なものと同じように、そうやって君に関するものを隠してきた」
言葉を止めてこちらを見たリジェネに、シンは軽い既視感を覚えた。
(オレは、この目を知ってる…)
何かを諦めて、大切な何かから取り残されたような。
「かつて『神』と呼ばれる存在は、自分を元に2人の人間を創った」
なぜここで、宗教上の物語が出て来るのだろう?
訝し気なシンの視線を受けても、リジェネに構う様子は無い。
「『神』は2人に知恵を与えなかった。知恵と引き換えに楽園を与えた。
彼らが知恵の実を食し知恵を手にしたそのとき、『神』は激怒した」
それは、人の始まりの物語だ。
リジェネは何かを嘲笑う。
「…私は時々、結局はそういうことなんじゃないかと思うんだ」
『神』はなぜ激怒したのか。
それは彼らに、知恵を手にされては困るからだ。
「自分を越えられては困るから、知恵を与えずに創った」
忌々しい、と声に出さず吐き出す。
どうやっても、ヴェーダのアクセス権を奪えない。
どれだけ厳重に鍵を掛けて仕舞い込んでも、それを暴かれてしまうことを止められない。
「私を創ったのはイオリア・シュヘンベルグじゃない。他の関係者でもない。
私はリボンズ・アルマークによって創られ、存在しているんだ」
リボンズは、自分よりも能力の低いイノベイターを創った。
決して自分を越えられないように、己が頂点で居続ける為に。
ややあってシンが投げた言葉は、以前にリジェネが零した言葉への問いだった。
「……それが、"生まれが違う"っていう意味?」
リジェネは頷きを返す。
「そうだよ。私以外のイノベイターは、私よりもずっと前に生み出された。
イオリア・シュヘンベルグと、彼の跡を継いだ者たちに」
けれどシンは、答えを求めているわけではなかった。
(やっと、分かった)
なぜ、彼の浮かべる表情を知っていると思ったのか。
(あれは…オレと同じなんだ)
刹那の手を放した瞬間から、再び掴んだその日までの、自分。
「昔はここまで思うことはなかったよ。でも計画が加速し始めて、顕著に視えるようになった」
私は他のメンバーのように、特別何かに秀でているわけではないから。
まるで自嘲のようなそれを聞いたシンは、握っていた拳をさらに強く握り締めた。
「…それ以上、言うな」
せめて昼間であったなら、ここまで強く思いはしなかった。
耳を塞ぎたくなる程に、過去を思い出すことが苦痛だと考えはしなかった。
「アンタ、自分がどんだけ酷い顔してるか分かってる…?」
刹那に再会して塞がったはずの、絶望という名の奈落の底。
きっとリジェネが見ているそれは、シンに見えているそれと同一のものだ。
「…なんでアンタを敵だと思い切れなかったのか、少しだけ分かった」
まるで音叉のようだと思う。
自分たちはまったく違うはずなのに、抱える闇のどこかが共鳴している。
「アンタはオレに似てるよ。リジェネ」
どこが?という顔をされたので、シンは笑った。
なぜ笑みを浮かべたのか、リジェネには解らなかっただろう。
おそらくそれは、シンが今まで彼と関わり続けてきた理由だ。
だから答える代わりに、彼の言葉に"応えた"。
…相手が人でない恐怖は、すでに消えていた。
「いいよ。アンタの話、全部聴いてやる。それがアラビアンナイトみたいに長くても。
けど、その代わり…」
オレの話も、聴いて。
明けぬ宇宙(ソラ)で千夜
ー ただ、誰かに聴いて欲しかった ー
09.3.12
考えていたはずの話と180°違う。なぜ。
とりあえず、リジーとシンの+が×に見えたら良い。
前の話へ戻る←/→閉じる