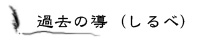 4
4
すべてを失った。
遺ったのは、家と、名前と、自分の命。
「まるで、道化を演じているみたいだ」
5年前、実の両親を亡くした。
手に遺っているのは、あのときと同じもの。
アメリカ合衆国西海岸、カリフォルニア州ロサンゼルス郊外。
広い敷地を持つ家がぽつぽつと点在するそこに、あまり生活感のない屋敷がある。
もちろん庭の隅々にまで手入れが行き届いているが、活気がない。
屋敷の人間は現在20人ほど。
主不在が1年以上続き、少しずつ働く気力を奪っていく。
「マリーさん、そろそろ休憩にしませんか?」
5年前に入ったもっとも新参の、ソウカという若いメイドがそう進言する。
屋敷の1階北奥にある物置の掃除を始めてから、確かに2時間近くが経過していた。
「そうねえ…そうしましょうか。ここは私がやっておくから、貴女はお茶の用意をしてくださる?」
「はい!」
ソウカが元気よく駆け出して行くのを見送って、マリーはやれやれと腰を叩き立ち上がった。
20年ほど前からこの屋敷に仕えて、マリーは今年50歳を迎える。
ふとするとため息をついてしまうので、気をつけなければ。
何年か前からメイド頭としてこの屋敷の者たちをまとめてきたが、暗雲が広がるように気持ちが沈むのは止められない。
「ふぅ…」
ああ、またため息をついてしまった。
手をはたいて窓から外を見てみると、沈む気持ちなどお構いなしの晴れやかさ。
薄雲が流れる青空も、この屋敷の暗雲を払うことは出来ない。
廊下を歩きながら、電灯や床、窓のチェックをする。
いつから習慣化されたのか分からないその癖は、この屋敷と共にある。
「せめて、消息をはっきりさせてくだされば良いのに…」
世の中が終戦して半年近くが経つ。
ほんの数ヶ月前まで、この屋敷は騒然とさせられていた。
『戦犯』…と露骨には言われなかったが、こちらが仕えていた主人について軍の人間が家捜しをして行った。
血気盛んでもなく控えめにしていったのは有り難かったけれど。
それでも各部屋はすべてひっくり返されたに等しい。
すべての物を定位置に戻すのにかなりの時間を要したことは、記憶に新しかった。
廊下の角を曲がると、向こうから顔なじみが歩いて来る。
「ああクーロン。貴方もお茶にしませんこと?」
ピシッとしたスーツを着こなすやや老いた男性は、マリーに気付くと足を速めて追い付いた。
年齢はマリーよりも10歳上で、髪も口髭も真っ白だが豊かに蓄えられている。
20年以上この屋敷で執事をやっていて、マリーよりも家の内情外情に詳しいのが彼だ。
「これはマリーさん。嬉しいお誘いです」
連れ立って1階西奥にある厨房へ向かう。
お茶の用意をするソウカやコックたちの横を通り過ぎ、隣の休憩室へ。
使用人たちに与えられたこの休憩室はそれなりの広さで、控えめな豪華さが却って心地よい。
また警備室の監視カメラの映像の一部が2台あるTVの片方に繋がっており、これがまた便利だ。
繋がっている映像は玄関先と門が映る2台分のカメラ映像。
マリーとクーロンは、いつものようにそれがよく見える位置に座った。
「1年…」
無意識のうちにマリーが零した呟きを、クーロンはしっかりと聞き取った。
「長いようで短い。もう1年も経ってしまいましたか」
何が、とは言わない。
「…そろそろ、企業側が五月蝿くなるかもしれませんわねえ」
マリーも問い返すことはしない。
クーロンはマリーの物憂げな言葉を、逆に少し軽く返した。
「確かにそのような時期ではありますが…。しかし、そちらへの圧力があるようですよ」
「え?」
初めて聞く情報に、マリーは顔を上げる。
「奥様が信頼を置いていた弁護士の方がいらっしゃるでしょう?旦那様はその方に財産管理をお頼みしておりました。
その方を先日、お尋ねしたのです。するとこんなことを仰いましてね」
「何と…?」
マリーはクーロンを注視した。
彼は部屋の中に視線を走らせ、わずかに声を潜める。
「企業側に圧力を掛けているのは"本部"です。ところがその本部に圧力を掛けている人物が…」
そこで言葉が不自然に途切れた。
クーロンは監視カメラの映像に気を取られたらしい。
マリーがそちらを見上げると、外門に1台の車が横付けされていた。
「まあ、お客様?」
前庭に放されている犬たちが、玄関カメラの視界へ集まっている。
3匹の犬はいずれも、すでに亡いこの屋敷の奥方が可愛がっていた犬だ。
屋敷の敷地へ入るための外門。
そして屋敷に入るための玄関。
どちらも屋敷内部の人間を介さずに通ることが出来るのは、ごく限られた人間だけ。
指紋や網膜を照合する最先端セキュリティが、この屋敷に設けられているためだ。
たとえば、この屋敷で働く者を取り仕切るマリーやクーロン。
不在となっている、この屋敷の主たち。
だからこそ、隣の警備室へ繋がるインターホンが鳴らされるのだと思った。
「「?!」」
休憩室のカメラ映像を見ていたマリーとクーロン。
その部屋へお茶を持って入ってきたソウカと、厨房のコックやメイド。
警備室に常駐する警備員たち。
彼らは一様に言葉を失った。
外門が開いた。
屋敷の内部を介さずに。
次の行動がもっとも素早かったのは、ソウカだった。
彼女はお茶のセットをテーブルに置くが早いか、身を翻して休憩室から駆け出していく。
半瞬遅れて部屋を飛び出したマリーは、若いって羨ましい、と場違いなことを考えた。


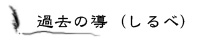 4
4