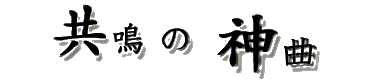Sympathizer07... 歌声は平和を導くか
アロウズの高官が集まるという、夜会。
自分も中へ潜入したいと願い出た刹那を何とか押し止め、ティエリアは単独、招待者として潜入する。
(奴らの狙いは刹那だ。リボンズ・アルマークという人間がここに現れるというなら、なおのこと)
彼に会わせるわけにはいかない。
ティエリアは時間を確認し、屋敷へと足を踏み入れる。
当然ながら、足元がまったくもって落ち着かない。
ミス・スメラギが自信を持って言い出した作戦だが、ティエリアにとってはかなり不本意であった。
(…なぜ女装など)
しかもすべてのクルーから大丈夫だと太鼓判を押されてしまっては、情けない気持ちにもなろう。
刹那にまで言われては、後にも退けない。
会場はすでに人が集まり、多くの重要人物が目に入った。
(なるほど。最高クラスの幹部まで来ているのか)
話し掛けてきた何人かへ当たり障りのない返答をしていると、人々がざわめいた。
「見ろ、王留美だ」
「なんと美しい…」
クリームイエローのドレスを纏った彼女は、ティエリアを見て意味ありげに笑った。
(…気に食わない)
彼女を見送ると、さらに別のざわめきが上がる。
「これはご当主!」
「本日はお招き預かり、光栄です」
薄緑の髪をした、ティエリアとそう年の変わらない青年が入ってきた。
ティエリアは直感的に悟る。
(こいつが、リボンズ・アルマーク!)
自分から『ヴェーダ』を奪い、『ラグナ』までもを狙う存在。
周囲の挨拶を受け取りながら、彼は至って自然にティエリアへ水を向けた。
「やあ。アナタが本当に来て下さるとは思いませんでしたよ、レディ」
【まさか本当に乗り込んでくるとはね。ティエリア・アーデ】
聞こえる声と響く声は、まったくの別物だ。
だからティエリアも、同じように返す。
「この度はお招き頂き、ありがとうございます」
【お前がリボンズ・アルマークか。知った風な口を利く】
何とまあ、相手の演技の巧いことか。
刹那と良い勝負なんじゃないか、と場違いにも思った。
リボンズはひょいと肩を竦めてみせ、ティエリアへ左手を差し出す。
「一曲踊って頂けませんか?」
そう、今のティエリアはどこからどう見ても、"美女"なのだ。
(さて、どうしたものか)
踊っている間なら、確かに邪魔は入らない。
ティエリアが逡巡したそのタイミングで、より一層大きなざわめきがホールを包んだ。
リボンズが入り口を振り返り、ちょうど良い、と呟く。
「良い機会だ。彼女にもご紹介しましょう」
見上げた2階の入り口から降りてきたのは、桃色の髪を靡かせ、エメラルドグリーンのドレスを纏う女性だった。
付き人を1人従え、彼女は一同を見渡して礼をする。
「こんばんは、皆様。遅れての参上、お許しくださいね」
ふわり、と彼女が浮かべた微笑みは、彼女が『聖女』と呼ばれる所以だ。
留美は女性を遠目に見上げて、目を見開く。
「ラクス・クライン…!まさか、彼女までが招待を受けていたと言うの?」
放送、と呼ばれる公共電波が届かない環境に居ない限り、彼女の存在を知らぬ者は居ないだろう。
…世界の歌姫、ラクス・クライン。
それが彼女を示す、もっとも知られた称号だ。
彼女はホールへ降り立つと、まっすぐにリボンズへ歩み寄った。
「お久しぶりですわ、リボンズ様」
リボンズもまた差し出された彼女の手を取り、その甲へ挨拶の口付けを贈る。
「これはラクス様。お忙しい中おいで頂き、恐縮です」
「あらあら。わたくしのスケジュールの隙間を付いたこの日。
相変わらず口がお上手ですこと」
ところで、そちらのお方は?
にこりと微笑まれ、ティエリアは軽く頭を下げる。
当たり障りのない紹介をされ、ラクスはぱんと軽く手を合わせた。
「これから踊られるのなら、遅れたお詫びにわたくしの歌ではいかがですか?」
「それは光栄です、ラクス様。貴女の歌声でステップを踏むなど、そうそうありますまい」
「では…曲はワルツで?」
「ええ」
ティエリアは仕方がない、と割切ることにした。
自分に最低限の女性ステップを教えた戦術予報士に、余計な世話だと文句を呟きながら。
ラクス・クラインの歌声は、確かに美しかった。
美しく、強く、誰もの心に訴えかける。
彼女の歌で、彼女の声で行動する者も多いということにも頷ける。
すべての回答は、まだ得られていない。
続きは場所を変えて、と告げられたティエリアも、断る理由は無い。
すると、歌の称賛を受けていたラクスが駆け寄ってきた。
「お待ちくださいな。リボンズ様、少しこの方とお話しさせて下さいませんか?」
このように同年代の女性と話す機会が、最近は少なくて。
そう苦笑したラクスに、リボンズはあっさりと承諾した。
「では僕は、皆へ挨拶に行きましょう」
彼はまた後で、とティエリアへ耳打ちし、立食の始まった会場の中心へと去る。
「とても素敵なワルツでしたわ、アーデルハイト様。
ですが、あまり舞踏会にはお出にならないタイプとお見受けしました」
問われたティエリアは、やはりバレたかと苦笑した。
「ええ。このような場は、好きとは言えないので…」
そうですの、と相槌を返したラクスは、じっとティエリアを見つめる。
「あの…?」
居心地が悪くて思わず声を掛けると、彼女はくすりと笑みを零した。
「いいえ。貴女の眼は、ロシアンレッドなのだと思って」
「え?」
「わたくしの義理の弟は、とても綺麗なルビーレッドですの」
瞬時にティエリアの脳裏に浮かんだのは、刹那の弟だ。
あのような色は、よほど極端なアルビノでなければ生まれ難い。
つまり、シンはかなり特異な性質を持って生まれたのだろう。
やや不可解な表情を浮かべたティエリアに、彼女は自分の右手に嵌めていた指輪の1つを手渡した。
とてもシンプルなプラチナの台座には、小振りのルビーが嵌められている。
ティエリアが問うように彼女を見返せば、ラクスはミステリアスと称される笑みを向けた。
「その指輪。貴女の知っているルビーレッドの眼をした方に、差し上げて下さいな」
雲より高いプレミアものですわ。
わけの分からない注釈を付けたラクスは、軽く頭を下げるとパーティへと戻っていった。
ティエリアはぽかんと彼女を見送る。
「これは凄い。彼女に気に入られたのかい?」
ラクスがティエリアに手渡していった指輪を窓辺の月明かりに翳し、リボンズは嘆息する。
「…なんとまあ、彼女の財力が見えるね」
これは最高級のルビーだ。
また手元に戻ってきたルビーを、ティエリアは改めて検分する。
宝石の価値などどうでも良い。
だが彼女の言葉だけは、いつまでもティエリアの記憶に残っていた。
ふわり舞う謎に惑う
ー あなたに歌を届けましょう ー
08.12.10
ラクスとユフィの話し方がごっちゃになってるらしい…。
設定として、クライン家は政治家としても有名です。
ティエの偽名は「アーデルハイト・シュヴァルツェ」にしてみた。ドイツ語。
前の話へ戻る←/→閉じる