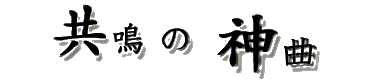Sympathizer13... 私たちは、生きています
ちっぽけな煉瓦作りの小さな家。
ここに隠れ住むようになって、もうひと月が経とうとしている。
胸の内に広がる不安は、増大するばかりだ。
今は夕食の時間が終わり、子供たちとマリナがお喋りに興じている。
ふと、ただ1台残っている端末をシーリンと見ていたクラウスの携帯電話が着信を告げた。
「これは…!」
番号を見て驚いた彼に、シーリンもマリナも何事かと彼を見返す。
「クラウス?」
彼は動揺という感情が周囲に与える影響をよく知っていて、それを表を出すことを滅多にしない。
だからこそ、子供たちも何だろうかとお喋りを止めた。
クラウスは未だ着信を知らせ続ける電話の、通話ボタンを押す。
「もしもし?」
《Hello World. あんたが望む世界は何色をしてる?》
番号は、たった1度だけ連絡を取った相手のもの。
間を置かず相手から問われたのは、相手を確認するための暗号。
ホッと息をついて、クラウスは答えた。
「Good-bye sadness. 青い空が見えるよ」
彼の言葉で、シーリンはハッと目を見開く。
「シン・アスカ…?」
青いガンダムが1度カタロンの基地を訪れ、去った後にやって来たという青年だ。
誰よりも彼に動揺したのは、マリナだったという。
「シン…?あの子が?!」
マリナはクラウスへ駆け寄る。
電話向こうの相手の、軽い笑い声が聞こえた。
《アンタたちは生きてたんだな。もっとも、生きていて貰わないとオレの仕事が無駄になる》
彼はカタロン基地を訪れ、マリナにガンダムのパイロットの話を聞いたという。
そうして彼女たちの作った歌の話に、こう言った。
『その歌を、世界中の人に聴かせたいか?』と。
シン・アスカは早々に本題を告げた。
《やっと準備が終わった。って言っても、相当に前倒しなんだけど。
そこにマリナ・イスマイールは居る?》
「ああ。替わろうか?」
《いや、別に良い。そこにラジオはある?》
「あるが…それが何か?」
《じゃあ、今すぐオレの言う周波数に合わせて》
何だかよく分からないが、とりあえず別の棚の上にあったラジオを手に取る。
言われた周波数に合わせると、パーソナリティが何事か話していた。
音量が小さくなっていて、聞き取れない。
《そのまま、聴いて》
それっきり相手は黙ってしまい、仕方なく携帯電話をテーブルへ置いてラジオの音量を上げた。
すると、先程聞こえた声ではない女性の声が響いてきた。
【……ですから、わたくしはこの歌を、宇宙に居る人々にも届けたい。
そしてこの歌を作られた方々が、安らぎを得られることを切に願っております】
子供たちが歓声を上げた。
「あ、これらくすさまだ!」
「知ってる!すっごく綺麗な歌の人!」
マリナは戸惑いを隠せない。
「ラクス様…歌姫ラクス・クライン?なぜ?」
もの問いた気なマリナとシーリンへ静かに、とジェスチャーを向け、クラウスは子供たちにも同じように示した。
そうしてしばらくして、流れて来た曲は。
「そんな…!」
誰もが絶句した。
その曲は、マリナが子供たちと共に作った歌だった。
パイプオルガンの荘厳で繊細な音色をバックに、ラクス・クラインの美しい歌声が素朴な詩を歌い上げてゆく。
このような山奥にも届く、周波数さえ合わせられれば誰もが聞くことの出来る局だ。
今この瞬間に、どれだけの人がこの歌を聴いているのだろうか。
長くはない歌が終わり、最後の音が消える。
マリナもクラウスもシーリンも、子供たちさえ無言だった。
再びパーソナリティの声が入り、歌の主であるラクスはそれに礼を言って出番を終えたらしい。
それ以降はパーソナリティの興奮した中継が続いていた。
《……》
「!あ、ああ、すまない」
テーブルに置いていた携帯から声が聞こえ、クラウスは慌てて電話を取った。
《マリナ・イスマイールに替わってくれないか?》
無言で渡された電話に、マリナは数瞬迷ってから答えた。
「…もしもし?」
《今の歌、さっきの番組が初披露だったんだ。まずはそのラジオから出発すると、ラクスは大々的に宣伝を掛けた》
「!」
《だから、彼女のファンはかなりの確率で今の番組を聴いていた。
時差があろうが関係ない。国が違って聴けないのなら、きっとネット上で探すよ》
出来ることなら、と願ったささやかなものが、現実となっている。
携帯電話を持つ手が、震えた。
「私たちの、子供たちの歌が、世界に…?」
そうだよ、と相手は答えてから訂正する。
《名前はアンタのだよ、マリナ・イスマイール。いずれは、それを公表する時が来る》
膝の力が抜けて座り込んでしまった彼女から、クラウスはまた電話を受け取った。
「…君の協力に、心から感謝する。これは、必ず我々の力になる」
《オレは歌のテープを彼女に渡しただけ。だから、生き延びて直接礼を言いに行けばいい》
クラウスは空いている手をぐっと握り締める。
「…ああ、その通りだ。いつか必ず」
通話が切れても、彼はしばらく携帯電話を見つめていた。
「電話の相手は、何者なの?」
尋ねたシーリンに、クラウスは曖昧に返す。
「私もよくは知らないんだ。ただ、CBのエージェントだと」
「CBの?」
ようやく立ち上がったマリナは、自然と流れた涙を拭って彼の言葉に続けた。
「…彼は、刹那の弟。双子で、びっくりするくらいに彼とそっくりで」
シーリンにも、ようやく合点がいった。
「刹那・F・セイエイの…」
するとそこで、あ!と子供の1人が大きな声を上げる。
「どうしたの?」
マリナが問えば、その子供は心底残念そうにラジオを見つめた。
「せっかくラクス様が歌っていたのに、テープに録らなかった」
思わず、誰もがくすりと微笑んでいた。
差し込んだ歌と云う光
ー どうか、戦う以外の方法を ー
09.3.1
時間軸がまったくもって違いますが。
「カードに例える話」のラクスの言葉は、こういうことです。
前の話へ戻る←/→閉じる