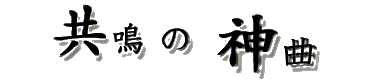Sympathizer14... 奈落の底に空を見る(前)
ユニオン圏の、とある別荘地。
(あーあ。平和だなぁ…)
庭と言うには広すぎる庭を硝子越しに見つめ、誰ともなくシンは呟いた。
現時刻は午前0時を回ったところだ。
CBやカタロン、軍から一歩離れれば、こんなにも連邦国家は平和だった。
ここは、王留美の持つ別宅の1つ。
好きに来て使っていいと言われたので、シンはごく稀にここを訪れる。
と言っても大抵、屋敷の主は留守だ。
住み込みの使用人が何人か居り、彼らが屋敷の維持に努めている。
だから、勝手に一泊したりするにはちょうど良い。
空を見上げれば、満点の星空が見える。
(刹那は、大丈夫かな…)
軽くはない怪我をしていると聞いた。
本人であれば"問題ない"と言うだろうが、シンに連絡してきたのはティエリアだ。
聞いただけなら彼は落ち着いていたけれど、実際はどうだろうか。
数日の行方不明の後にようやく再会したと思ったら、刹那は重傷を負っていた。
自分だったらきっと、頭が真っ白になる。
(今は『ラグナ』も余裕が無い。だから、なおさらだ)
『ヴェーダ』とイノベイターの『ラグナ』に対する妨害は、相当なものだ。
本来の力の7割でも発揮出来れば、良い方だろう。
世界を網羅するレベルで完成されている『ヴェーダ』と違って、『ラグナ』はそちらの分野で未完成だった。
本家CBに悟られぬよう密かに動いていたスローネは、大々的に物事を押し進めることが出来なかったのだと言う。
それに、イオリア・シュヘンベルグという中心人物が居ない組織は、たとえ理念が同じでも人を集められなかった。
不意に、ポケットに入れていた携帯電話が震える。
誰だろうかと端末を開けば、見覚えのある番号が表示されていた。
(これって…)
この数字を見たのはそう遠い日ではない、ごく最近だ。
「もしもし?」
通話ボタンを押せば、聞こえてきたのはやはり知っている声。
『こんばんは。君の居る場所が、夜だったらの話だけど』
なぜこの番号を知られてしまったのか、分からない。
かといって、用心に番号を変える必要性も感じてはいなかった。
「…リジェネ・レジェッタ」
相手の名前を返せば、クスリという笑い声が返る。
『そうだよ、シン・アスカ。ところでそこは何時なの?君はいつも違う場所に居るから』
時間を答えることは即ち、自分の居場所を知られるということだ。
嘘をつくことも容易いが、シンは嘘というものが大嫌いだった。
「…"こんばんは"の通じる時間」
だからそれだけを答える。
すると電話向こうの相手は笑ったようだった。
『そう。なら良かった』
けれどリジェネは、それ以降に何も言葉を発しない。
通話を切るにも切れず、いったい何なんだとシンは困惑する。
(何でこんな時間に…いや、夜の挨拶が通じる時間なんて夕方から翌日まである)
しかし、確信のような疑問が残る。
(驚く様子も無かった。オレが電話に出ることを予期してたみたいに)
今まで幾度となく遭遇したが、それはシンにとってであって、リジェネには"遭遇"ではないだろう。
(なんでコイツは、いつもオレの居場所が分かった?)
ふと脳裏を過ったのは、シンの家族とも言える情報屋の言葉だ。
ーーー王留美には、気をつけた方が良い。
それを教えてくれた彼は、リジェネを警戒対象とは見ていなかった。
シンは散らばる情報の断片を繋ぎ合わせ、電波が繋ぐ通話の向こうへ問い掛けた。
「アンタは、王留美と繋がってるのか」
疑問ではない"断定"は、次に相手が返す言葉で真偽が知れる。
『…なかなかに面白い意見だね』
シンは自分の仮定が外れていないことに確信を持った。
「やっぱり。だからアンタは、オレの行く先に現れることが出来た。
オレはCBのエージェントみたいなものだから、行動起点は必然的に王留美の拠点になる」
それならば、いくらでも情報を掴める。
するとリジェネが声を出して笑った。
『あははっ、さすがだね。"GARMR&D"を名乗る人間は、誰も彼も油断ならない』
誰のことを言っているのだろう?
「…誰に会ったの?」
眉を寄せて問えば、こっちの屋敷に単身で乗り込んできたよ、と言われた。
『"月光"と呼ばれてる、傭兵みたいだね。詳しくは私も知らないけれど』
十中八九、カナードのことだ。
再び会話が途切れ、シンは自分の声がやけに響いている気がしてならなかった。
とにかく、客間だというのに部屋が広すぎるのが悪い。
『…彼女は、』
不意に紡がれた三人称は、王留美を差しているのだろうか。
シンは聞き逃すまいと神経を研ぎ澄ませた。
『王留美は、私とリボンズが同じだと思っている。
だから、リボンズに見限られても望みを掛けられるように、私に近づいてきた』
考えるまでもなく、言葉には侮蔑が乗っていた。
『彼女は人間だけれど。少なくとも、人々が求めるすべてを持っているように思うよ』
その通りだろうとシンは1人頷く。
彼女は富も権力も美貌も聡明さも手にしているのだから、願いの98%は確実に叶うはずだ。
『これ以上、何を求める必要があるんだろうね?』
何が言いたいのだろう、彼は。
途切れた言葉の先は、まったく違う話だった。
『ねえ、シン。君は"イノベイター"という存在について、どこまで知ってる?』
まったくもって意図が掴めないが、隠す必要はないだろう。
「…あまり人数が居ないこと」
『うん』
「脳量子波を使えること」
『そうだね』
「よく分からないけど、CBとは別の役割がある」
『そう』
「"戦闘用"とか、それぞれに得意分野がある?」
『…まあ、ね』
何だ?とシンは思わず携帯電話を見つめた。
…反応が違う。
「リジェネ?」
思わず名前を呼べば、ややあってまた声が続いた。
『…君は、自分の名前が好き?』
またも話が飛んだが、シンは当たり前だと返した。
「好きだよ。だって、両親がつけてくれた名前だ」
昔は、好きか嫌いかなんて感じることも無かったけれど。
「だって刹那が、刹那が"絶対に捨てるな"って言ってくれた…名前だから。
やっと会えたあの日まで、刹那がずっと呼び続けてくれた名前だから」
そう、と返してきた言葉の主の、真意は何なのだろうか。
「…何なんだよ」
黙って不可解なやり取りを続けるには、限界だった。
「オレは"あの人たち"みたいに賢くないから、アンタの言いたいことが分からないよ。
何が言いたいんだ?何を言いたいんだ?オレに何を求めてるんだよ!」
何よりも、相手の顔が見えないことが不快だ。
率直に告げれば、リジェネはまたしばしの間を置いて問うてきた。
『…君の居る、場所は?』
このもやもやとした不快感を削ぎたいが為に、シンは自分の居場所を明かした。
「けど、あんたの居る場所がどこかにもよるだろ」
日付も越えた時間に出掛けるなど、あまりやりたいことではない。
当然のことを言ったシンに、リジェネは笑って返した。
『気にする必要は無いよ。だって私は…』
庭を臨むガラス窓。
一番小さな明かりだけが灯された客間は、それでも十分に明るい。
硝子に映り込む自分の姿を見たシンは、そこに見えたものにぎくりと身体が強張った。
…耳元にある携帯電話から、声が聞こえる。
「『座標さえ分かれば、そこへ辿り着けるからね』」
肉声と音声が重なっていた。
(う…そだろ…?)
恐怖で身体が凍りついてしまい、振り向けない。
銃を突き付けられても、こんなことにはならないのに。
人間?本当に?
ー 人ではないのだと、見せつけられた ー
09.3.2
小話部屋にまったくもって収まる長さじゃない。×2(…)
地味に広げようリジェシンの輪!(←開き直った)
前の話へ戻る←/→閉じる